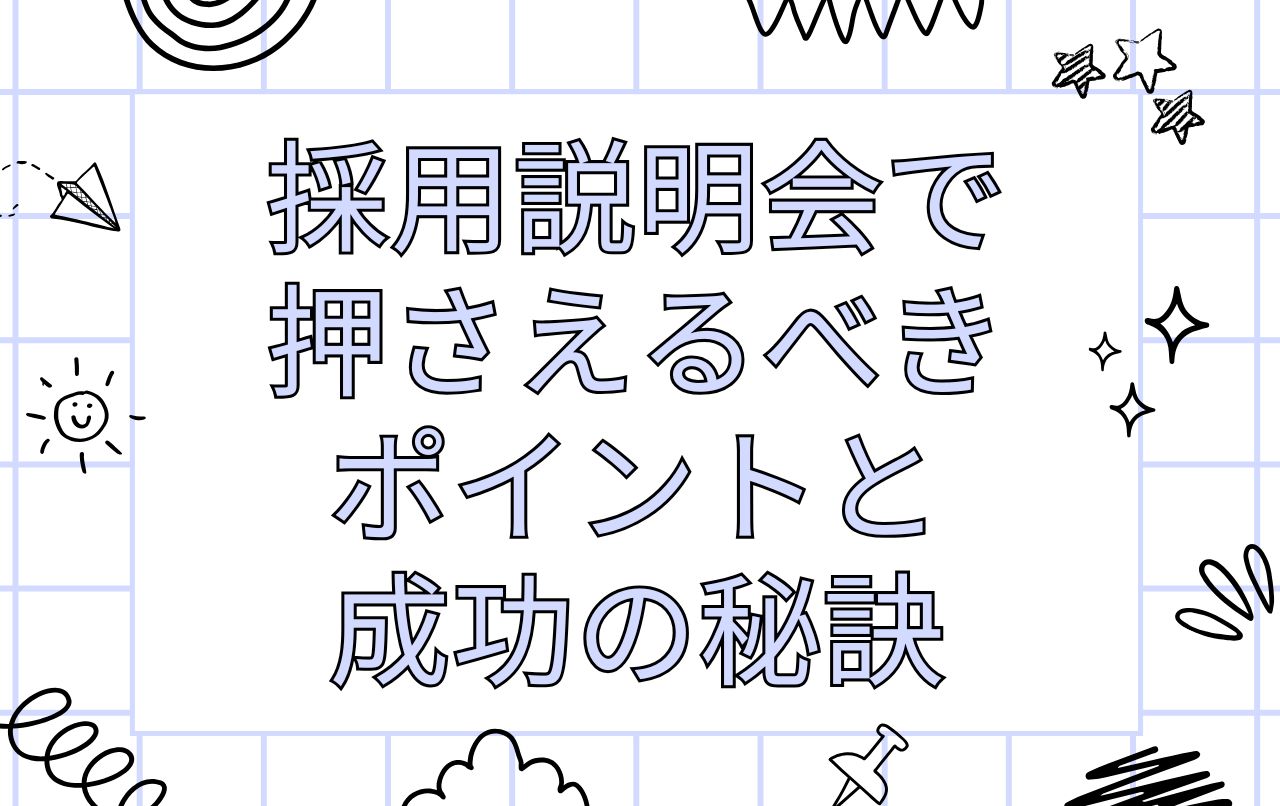
求職者にとって採用説明会は、自分が情報収集した情報以上の情報を求めて「この会社で働きたい」と思うか否かを図る貴重な時間となります。企業としても求職者と関われる貴重な機会となりますので、有益な時間にするために内容を充実させたり、事前にしっかりとした準備をすることが重要です。
「とはいえ、はじめて採用説明会をしたいと思うけど何をすれば良いかわからない」
「採用説明会に必要な準備と方法が知りたい」
そんな採用担当者の方のために本記事では説明会の流れや、成功のためのコツをまとめました。
選ばれる企業の説明会を目指して、準備していきましょう。
採用説明会の流れと選ばれる企業になるための説明のコツ
有意義な採用説明会を実施するためには、当日の流れをあらかじめ決めてその流れに沿って説明会を進行していくことが重要です。この章では会社説明会の流れと説明する際のコツをご紹介させていただきます。求職者に伝えるべきことを絞り、印象に残る説明会を実施しましょう。
採用説明会の一般的な流れは以下の通りです。
▼プレゼンターの自己紹介
▼会社概要(業界・会社の特徴)
▼仕事内容
▼働き方(現場の声)
▼採用・選考情報
▼質疑応答・社員との交流
▼アンケート改修・見送り
ご紹介する内容例は必ずしも全て入れる必要はなく、ターゲットや時間に沿って必要なものをピックアップするようにしてください。
【自己紹介】プレゼンターの自己紹介は親近感を持ってもらうことが重要
採用説明会のはじめには、プレゼンターの自己紹介をするのが一般的です。ただ役職や名前を紹介するだけでも良いですが、経歴や趣味、プライベートでの過ごし方など、身近な話題を入れることでより親近感をもってもらいやすい自己紹介になります。
採用説明会に参加してもらう社員には、行き当たりばったりの状態で会場にきてもらうのではなく、事前に時間を取り、自己紹介の流れを準備してもらった方が良いでしょう。また普段人前で話すことに慣れていない社員は人前で話す練習も十分に行った方が当日より普段通りの雰囲気を知ってもらいやすいです。
【会社概要】企業理念・ビジョンは興味を持ってもらう工夫が必要
採用説明会では自社がどのような会社であるのかを求職者に理解してもらうために、まずは会社の概要について説明をするようにしましょう。
会社の概要では一般的に下記を説明すると良いです。
・会社の歴史
・社名の由来
・会社のミッション
・商品、サービスのバリュー
・今後のビジョン、課題 など
しかし、これらの会社の情報をあれもこれもと伝えてしまうと、求職者にとっては逆に印象に残らず忘れられてしまう可能性があります。企業説明会ではあえてポイントを絞り事細かに説明しないように気を付けることが重要です。
特にどんな業界・会社なのかを簡潔にまとめ、他業界、他社との違いが明確になるような要素をまとめると良いでしょう。
また、説明の際に会社の良い部分だけでなく企業の弱みや課題に対し今後どう強化をしていきたいかを話すことでより話に納得感を与えることができます。
エピソードやストーリーなどを盛り込みながら聞き手を引き込める内容を考えましょう。
この項目は企業の創業者、経営者自身が話すことで説得力を高めることができます。当日スケジュール的に登壇が難しい場合には録画した動画を流すなど工夫をしましょう。
【仕事内容】業務内容は仕事のやりがいや成長の具体例を入れる
業務内容は具体的にどのような仕事をしているか伝えるようにしましょう。どのような案件があり、現場にどんな形で関わっていき、何の業務を担当するのか具体例を混ぜながら説明をすることで未経験の方でも自分が実際に働く姿や職場環境を思い浮かべやすくなります。
入社後に「こんな仕事と思わなかった」などギャップを感じる可能性を減らすためにも求職者目線の説明を心がけましょう。
この項目は実際にその業務を行っている人事部長や社員が担当すると仕事内容だけでなく苦労ややりがいなども説明できるため良いでしょう。採用決定権が事業部ごとにある場合は直接人材をチェックできるメリットもあります。魅力的なエピソードを盛り込むことで「自分も同じ経験がしてみたい!」と思ってもらえるような内容を目指しましょう。
下記に一例をご紹介します。
【営業職の仕事内容紹介の場合】
当社の営業職は、お客様との信頼関係を築きながら、コミュニケーション能力やプレゼンテーションスキル、交渉力などの多様なビジネススキルを磨き、努力が売上や成績に反映されることで達成感ややりがいを感じられる仕事です。私自身、入社して間もない頃、ある中小企業の経営者様から「業績が伸び悩んでいる」と相談を受けました。じっくり話を聞き、具体的な課題を洗い出した上で、当社の製品がどのように問題解決に役立つかを提案しました。その結果、導入後に業績が改善し、経営者様から「あなたのおかげで会社が変わった」と感謝された時の喜びは格別でした。
個人の努力とチームの協力が重要で、情報共有や勉強会を通じてチーム全体のスキルアップを図りながら、市場の最前線でお客様の声を直接聞き、新しいビジネスチャンスを発見することができる魅力的な職種です。営業職として働くことで、自己成長を実感し、お客様に真の価値を提供できる喜びを共有することができます。ぜひ一緒に成長し、成功を目指しましょう。
上記のように具体的な経験談やこの仕事をすることで得られる経験、能力を語ることで魅力的な仕事紹介にすることができます。
【現場の声】若手社員や先輩社員との交流機会を設け、企業の社風や雰囲気を伝える
参加者と社員との交流の場を設けることで、求職者に入社後のイメージを明確に持ってもらうことができます。
特に入社して間もない若手社員や実際に現場で働く際の上司など入社後関わっていただく機会の多い方と交流機会を設けることでお互いの入社後のギャップやアンマッチを減らすことにも繋がります。
また、若手社員の生の声を届けることで、職場環境や雰囲気など印象に残りやすく伝わりやすいメリットもあります。
この時、業種や部署に分かれ、少人数で質問をする座談会形式がおすすめです。
採用説明会終了後にまとめて質問を受けるでも良いですが、少人数で行った方が求職者の方も質問しやすく志望度が高まりやすいです。
【採用情報】募集要項や説明会後の選考フローを説明する
説明会の最後には、自社の募集要項や選考フローなどの採用情報について伝えるようにしましょう。
情報として伝えるべき内容は下記になります。
・求める人物像(スキルや性格など)
・職種別の採用予定人数
・配属予定の部署の説明、担当予定の事業
・初任給、待遇
・選考フロー、今後のスケジュール
求める人物像は入社後のミスマッチを減らすためにもできる限り具体的に伝えるのがポイントです。
「将来的にインバウンド向けの商品の開発に携わってほしいので、グローバルな視点がある方を求めている」「会社に新しい風を吹かせて欲しいので人材系の知識だけでなく幅広い経験を求めている」「体を動かす機会が多い仕事なので学生時代にスポーツをしていた方や運動が好きな方は是非選考にお越しください」などの伝え方をすると求職者にも納得感を与えやすいです。
合わせて、今後の選考フローなども説明するようにしましょう。予定が分かることで求職者もスケジューリングしやすく応募を促すことができます。
また、選考中の連絡手段やどのような課題を設ける予定などを説明することで、求職者も選考に向けてどう対策すべきかがイメージしやすくなるため不安なく本選考に進むことができます。
【アフターフォロー】採用説明会のアンケートで聞くことは少なくても大丈夫
採用説明会が終了したらアンケートを取るようにしましょう。
採用説明会のアンケートを実施することで、就活生が会社を知った理由や、説明会の内容で印象に残ったポイントを知ることができます。
これにより自社の魅力や強みを再確認し、今後の採用活動の取り組みを見直すことができます。
また、説明会後のアンケートを実施する際、注意が必要なのはアンケートの項目数です。アンケートの項目が多すぎると回答するのに時間や労力がかかるためマイナスイメージになりやすいです。結果、回答をしなかったり、適当に回答してしまう…などの可能性が高まります。
必要最低限の項目でも次回に活かせるような質問をするようにしましょう。
一例として下記のような質問が考えられます。
・採用説明会の満足度を知るための質問
「採用説明会全体に対する満足度をお答えください」「採用説明会の時間配分や内容は適切でしたか」「採用説明会に参加する前と後で企業に対するイメージは変わりましたか?」などの質問が考えられます。いずれも、「満足」「普通」「物足りなかった」や「はい」「いいえ」など選択を設け、理由を書く欄を設けると統計が取りやすくなります。
・自社のどこに魅力を感じたかを知るための質問
「採用説明会で一番印象に残った部分はどの部分ですか?」「採用説明会で好印象だったポイントはどこですか」などの質問が挙げられます。
「企業の事業内容やビジョンに共感できた」「職場環境や働き方が魅力的だと思った」「社員の話の内容が印象に残った」など、ある程度選択肢を設けることで応えやすくなります。
・求職者の志望度合いを把握するための質問
「現在の選考状況を教えてください」「現状の志望度を教えてください」「他社と比べて、良かった点、悪かった点を教えてください」などの質問が一般的です。採用説明会後の全体の志望度の把握をすることで、採用説明会の内容の改善に活かしていきましょう。
・採用説明会に参加した理由
「採用説明会のことをどこで知りましたか」「採用説明会に参加することを決めた理由は何ですか」などの質問が考えられます。
「業界に興味があったから」「仕事内容に興味があったから」「知人・友人・先輩に紹介されたから」「就活フェアなどで紹介をされたから」など選択式で応えてもらうのが一般的です。
【その他】企業独自の内容を説明会に盛り込むことが大事
求職者の印象に残る採用説明会にするには、独自の内容を説明会に盛り込むことも必要です。
良質な情報を伝えるだけでなく、インパクトに欠けてしまうと、他企業の採用説明会に上書きされてしまう可能性もあります。
数ある企業の中に埋もれてしまわないためには求職者に会社のことを知ってもらうだけでなく「楽しかった」「来てよかった」と思ってもらうことも重要です。
面白い説明会の例として下記のようなものがあります。
・仕事内容や事業内容を踏まえたグループワーク、ディスカッションなど
・会社や社内の様子が分かる動画を見せる
・先輩社員との座談会の機会を設ける
・実際に業務の一部を体験してもらう
・商品の裏話や他では聞けない内容を用意する
これら全てを盛り込むことが重要なのではなく、「独自の企業らしさ」が出せるように自社の社風や社員の傾向などに応じてカスタマイズしていくことが重要です。
人事担当者必見!採用説明会の事前準備
1章では採用説明会の流れやコツをご紹介してきましたが、実際のところ説明会成功の秘訣は事前の綿密な準備にかかっています。この章では説明会を実施するにあたっての必要な事前準備のポイントや手順などを段階ごとに詳しく説明していきます。
事前準備の方法は下記の通りです。
【手順1】採用ターゲットの設定をする
【手順2】説明会の種類、実施方法選定
【手順3】参加者の集客方法
【手順4】魅力的なスライドや資料を準備する
【手順5】求職者に好印象を与えるプレゼンを準備する
【手順6】当日のタイムスケジュール設定と時間配分の決定
【手順7】スピーカーなどの備品準備、設営案整理
【手順1】採用ターゲットの設定をする
採用説明会のターゲットが曖昧なまま説明会を進めると企業の良さが求職者に伝わらないものになってしまう可能性があります。まずは「どんな人を採用したいのか」を明確にしてからコンテンツの準備を進めましょう。
この際、「なんとなく若い人」や「能力が高い人」「人柄が良い人」など抽象的なターゲット設定は避けるようにしましょう。
「どのくらいの年代の方なら会社に馴染めそうか」「業務にどんなスキルが必要か」「どんな考え方をする人材がよいか」「採用後はどんな仕事を任せていきたいか」など具体的にペルソナを抽出するようにします。
ペルソナとはターゲットよりも詳細に特定の人物像を設定したものです。
例えば、営業事務職の採用を考えている際に「明るく元気でコミュニケーション能力が高い人」などだけではペルソナとしては少し抽象的です。
具体的に「営業職全般の事務サポートの業務を任せたいため基本的なPCスキルがあり、請求書や見積書などの作成業務の経験がある方、年齢層は社内が20代~30代が多いので30代くらいまでで募集したい。営業部とのやり取りやお客様との折衷業務なども稀に発生するためチームで作業するのに抵抗がない人」など自社の状況や現在実際に活躍されている社員の特徴から考えていくのが一般的です。
ペルソナの設定方法は下記の記事にもまとめているので参考にしてみてください。
▼【テンプレート付】欲しい人材を確実に採る為の採用ペルソナ設定方法
https://www.bsearch.co.jp/media/hiring-persona
【手順2】採用説明会の種類、実施方法選定(合同・個別・オンラインなど)
次に、採用説明会の実施方法を選定します。採用説明会にも、就職情報会社やハローワークなどが主催し開催する「合同説明会」や企業が独自で開催する「個別説明会」など種類があります。また対面やWebなど実施の方法なども多様化しています。この章ではそれぞれの採用説明会の特徴や必要な準備をまとめました。
合同企業説明会
合同企業説明会とは、複数の企業が同じ会場に集まり、一斉に行うのが特徴です。基本的に就活情報サイトや各地の自治体などが運営していることが多いです。首都圏や地方都市では規模感などは若干異なりますが、大規模なものになると数百の企業が集結するものもあります。参加者が多いためたくさんの求職者に向けて自社のアピールができることや、参加している他の企業の情報を収集することもできるなどメリットも多いので、説明会に慣れていない企業はまずは合同説明会からスタートしてみるのも良いと思います。デメリットとしては人気企業の参加も多いため、自社印象を残すのが難しいことや、ブースに人を集めるのが難しいことなどが考えられます。
個別企業説明会
個別企業説明会は、企業が自社内で行う説明会のことです。求職者にとっては、企業に行き実際の現場を見て、先輩社員たちと深くコミュニケーションが取れるなどのメリットがあり、企業側にとっても合同説明会よりもしっかりと時間を取って企業の魅力をアピールできたり、求職者ひとり一人と向き合って質問に答えたりできるので、選考まで繋がりやすいメリットがあります。
知名度があまり高くない企業は、参加者を集めるためにしっかりと事前準備をする必要があります。例えば求人広告で広報したり、採用サイト、SNSでも事前に発信するようにしましょう。可能であれば、事前申し込み制にすると当日の準備がスムーズです。対象者に合わせ、参加しやすい曜日や時間帯に開催時間を調整したり、オンライン配信にしてより多くの人が参加できるように工夫することも有効です。また、合同説明会と違い会場での備品準備や参加者の受付、誘導、アフターフォローなども自社で準備する必要があるので事前準備の工数は少し多くなります。 採用説明会に向けての事前準備は次章でも紹介しているので是非チェックしてみてください。
オンライン説明会
オンライン説明会とは、PCやスマートフォンなどを通じて、Web上で開催する採用説明会です。新型コロナウイルスの感染対策として取り入れ始めた企業も多いです。今では感染対策だけの観点ではなく、会場が不要で準備のコストを減らせることや、移動時間がないためスケジュールを気にせず気軽に参加できるため参加者が集まりやすいなどを理由に導入する企業も多いです。
リアルタイムで配信する形式や、対面式の説明会と同時に開催する形式、予め録画をしていた動画を配信する形式などオンライン説明会の中にも様々な形式があります。採用説明会の冒頭部分で企業説明の動画を流し、より印象に残る採用説明会にしてみるのも効果的でしょう。
オンライン説明会は対面で行うよりも参加者の反応を見づらいといったデメリットもあります。参加者に画面をONにしてもらい、表情や反応を見やすい状態にしたり、採用説明会終了後にアンケートをしっかり取るなど工夫が必要です。
【手順3】参加者の集客方法
採用説明会に来てもらうために、まずは会社を認知してもらうことが重要です。自社サイト上で採用を告知するだけでなく、求職者に気づいてもらえるようにブランディング含めた集客が必要です。
説明会の参加者を集客するための具体的な方法を3つ下記にまとめさせていただきます。
・大学や研究室に訪問する
新卒採用の場合は、学生が説明会に訪れるのを待つのではなく、企業側からも積極的にアプロ―チをしていくことが重要です。
「採用説明会に来て欲しい学生」に向け、企業の名前を印象付けることができます。また学生に直接会い、採用説明会への参加を促すことができるのもこの方法の強みです。
・SNSを活用して広くアピールする
会社のPRとしてSNSを活用するのもおすすめです。求職者の多くはSNSをプライベート含め情報収集に利用しています。そのため、そういった対象の方には自社サイトよりもSNSの方が会社情報を見てくれる可能性が高いです。
自社の情報をSNSで発信し続けることで、求職者も企業に対して身近なイメージをもってもらえるでしょう。
・求人広告で募集をする
マイナビ転職やリクナビNextなど就活総合支援サイトで、自社の求人や説明会の参加を促す広告を掲載するのも有効な手段です。
求人媒体で募集をすることで、就活への意欲が高い求職者を集められる可能性が高いです。
こちらの方法は登録者数も多いことから、自社を認知してもらえる機会は多いですが、その分競合も多くなるので、埋もれてしまう可能性があり、より魅力的な求人を作成する必要があります。
【手順4】魅力的なスライドや資料を準備する
採用説明会においてスライドやプレゼンテーションも重要な要素となります。スライドなどの資料を作成することで、視覚的な情報をプラスすることができます。口頭だけの説明だけだと、具体的なイメージができにくく、説明会全体が単調になりやすいので、視覚的にインパクトを与えるだけで印象に残りやすくなるメリットがあります。
この章では魅力的なスライド資料を作るためのコツをご紹介します。
読み手に分かりやすく情報を届けるスライドにするためにはできるだけ視覚的に入ってくる情報を絞ることが需要になります。
情報を詰め込みすぎているスライドは読み手の意識が散ってしまい、分かりづらくなってしまいます。
シンプルなスライドにするには以下のポイントを意識しましょう。
・ワンスライド・ワンメッセージ
「結局何が言いたいか分からなかった」そう思われないように、1つのスライドに込めるメッセージは1つに絞るように意識しましょう。
1つのスライドに伝えたいメッセージが1つに限定されていれば、読み手はプレゼンターが何を伝えたいのかがシンプルに考えることができるようになるため、メッセージ内容を理解しやすくなります。読み手の情報処理量を増やさない工夫が必要です。
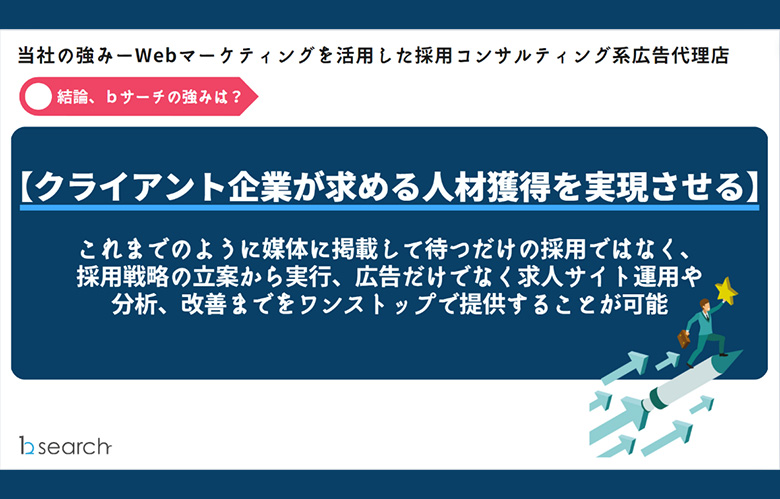
・画像やグラフに過剰な装飾をしない
スライドの見た目を気にするあまり、メッセージに直接関係のないイメージ画像やグラフ・文字を盛り込んでしまうとそれがノイズになり肝心のメッセージが伝わらなくなってしまいます。
なんとなくで色や装飾を多用するのではなく、色や枠線は意図や意味を明確に持たせるようにすると良いでしょう。
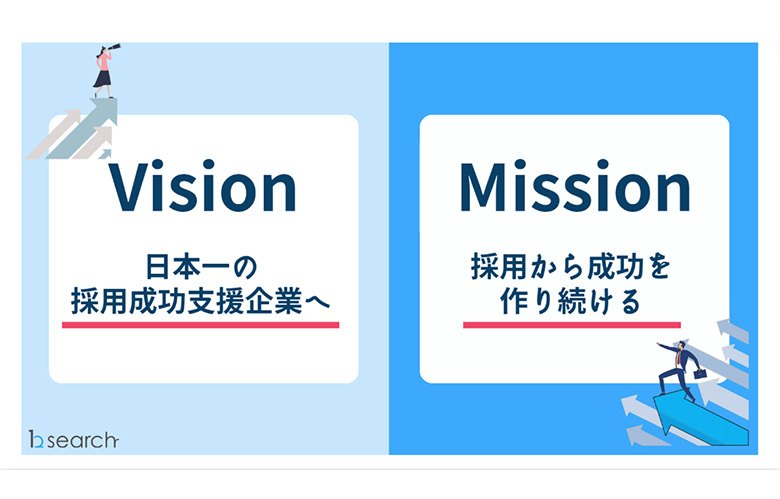
・スライドの内容は人の視線を意識した場所に配置する
ひとの視線の動きは左上から右下に流れる傾向があります。
そのため重要なことは最初に視線がいく上部に記載すると良いです。また、過去から未来といったように時系列や変化を表したいときは視線の流れに合わせて左に過去、右に未来を配置すると
自然に視線を誘導することができます。
また、人間は左目で見たものを右脳で処理するため、感覚的にとらえて欲しい写真や画像イメージなどはスライドの左側に配置すると印象に残りやすくなります。

採用説明会ではスライドを見せるだけではなく、スライドを見せながら説明などをすることが一般的だと思いますので、スライドはあくまで補足として使用するようにしましょう。
【手順5】求職者に好印象を与えるプレゼンを準備する
採用説明会においてプレゼンテーションも重要な要素です。
求職者に興味関心を持ってもらえるような内容のプレゼンを考えましょう。
人の興味は「親近感」から生まれやすい傾向があります。
どんなに良い商品やサービスでもただ説明されただけでは親近感を感じてもらうことはできません。この商品ができるまでに、こんな歴史があり、失敗があり、その結果何に活かされているのかなど、実際に起きたことをリアルに話し、ストーリー性を持たせることで、求職者にも親近感を持ってもたいやすくなります。
そして、説明会に来たからこそ得られる情報も求職者に興味・関心を持ってもらいやすいです。「実はこんなことがあった」という「ここだけの話」など参加したからこそ得られる情報があるのは特別感もあり記憶に残りやすいです。
採用説明会の説明をする際には企業の情報を一方的に話すのではなく「双方向コミュニケーション」を意識するようにしましょう。求職者に内容について意見を聞いたり、クイズ形式にしてみるなど、参加型の採用説明会にすることで、その場の一体感が出て、心理的距離を近づけることができます。聞いてる求職者の反応に応じて、質問を投げかけたり、意見を聞いたりして、双方に話やすい場を作っていきましょう。
【手順6】採用説明会当日のタイムスケジュール設定と時間配分の決定
採用説明会当日のタイムスケジュールを予め作っておくことも重要です。当日の流れを決めておくことでスムーズに進行することができ、突然トラブルが発生した場合も落ち着いて対応することができます。
具体的には、下記の流れでそれぞれ目安でタイムスケジュールを組んでおきましょう。
・求職者に対する説明
・休憩時間やプレゼンの時間配分
・質疑応答
参加者1人ひとりと時間を設ける場合は間延びしないように10分ほどの時間で設定すると良いです。
タイムテーブルを滞りなく進めるためには事前のリハーサルをするのがおすすめです。リハーサルをしっかり行い、それによって項目ごとの時間を削ったり増やしたり調節をします。段取りでもたつかないように入念にチェックしましょう。
【手順7】スピーカーなどの備品準備、設営案整理
採用説明会の実施方法、内容が決まったら、最後に採用説明会の運営にあたっても準備が必要です。
採用説明会の実施方法によって必要な準備や備品が異なるので、この章では実施方法ごとに必要な準備をご紹介します。
〈オンライン説明会の場合〉
・使用するツール(ZoomやTeamsなど)、推奨環境、カメラをON/OFFなどの情報を確認し、参加者に広報する
・会議室など静かな環境を用意する
・背景に映り込みがないかをチェックする
・プレゼンター以外にシステム管理者を決める
・通信環境をチェックする(逆光になってないか、音声は問題なく聞こえるか)
〈対面開催の場合〉
・必要な備品の準備(会場の椅子、プロジェクターの準備、マイク)
・備品の配置や動線などのチェック
・参加者の選出、スケジュール管理
・人事以外の社員にも説明会の開催を広報し、求職者への挨拶を心がけてもらう
・本番前のリハーサル
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事では、採用説明会のコツと必要な準備についてご紹介してきました。
採用説明会は求職者にとって情報収集の機会であると同時に企業側にとっても求職者の方と関わったり、他企業の動向を確認できる貴重な情報収集の機会です。せっかくの機会を最大限活かすためにも事前準備を入念にし、選ばれる企業の採用説明会を目指して説明会の内容をブラッシュアップしていきましょう。
最初のうちは、「集客ができない」「説明会を実施してもなかなか応募につながらない」などがあると思います。そんな時は求人広告を出したり、就職フェアに参加するなどがおすすめです。株式会社bサーチでは、就職フェアなどイベントのご紹介、求人原稿の作成やその後の採用代行など一貫して企業様の採用サポートを行っています。
興味がある方はまずはご相談からでも是非お問い合わせください。

コメント